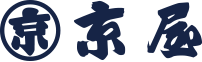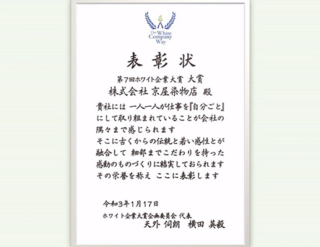京屋染物店について
about

京屋染物店は岩手県南の城下町「一関(いちのせき)」で100年続く染物屋です。
世界遺産平泉の浄土思想や伝統芸能、数多くの伝統工芸品が生まれたこの地で、お客様だけのオーダー品を想いやこだわりに寄り添い、心を込めて大切に作り上げています。
私たちは、単なる「染物屋」ではありません。
100年積み上げた経験値のもと、チャレンジ精神溢れ創造力豊かな職人が、お客様のこだわりを実現します。
商品一覧
product

LOCAL WEAR IWATE / *Snow Peak×京屋染物店
LOCAL WEAR IWATEについて詳しく
en・nichi(エンニチ)
en・nichi(エンニチ)について詳しく
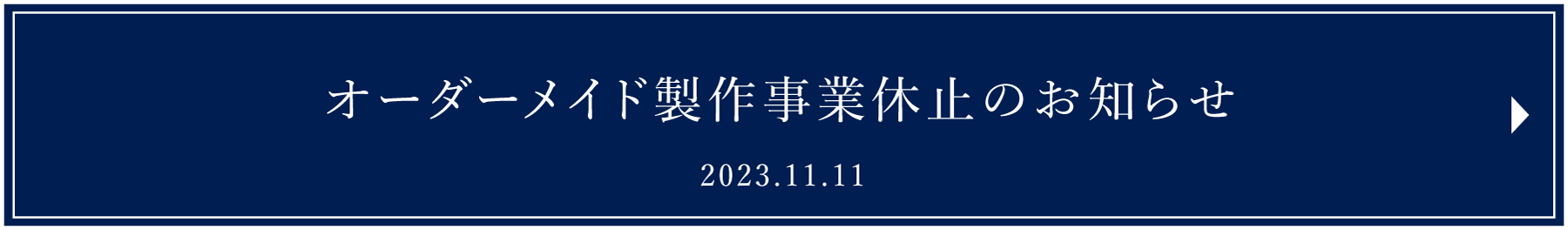
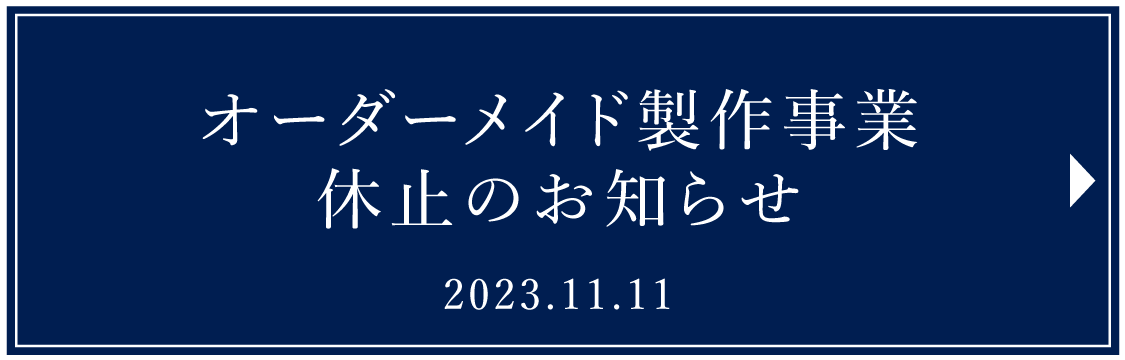

−安心・安全な商品を作っています。−
京屋染物店の工場では、染色プロセスにおいて、検査機関の厳正な審査で安全性を認められた素材・染料のみを使用しています。
また、生地の安全性にもこだわり、赤ちゃんの肌などに悪影響があると言われる”蛍光塗料”を使用していないものを特注で仕入れ、使用しています。
全ての製造フローで安全性に配慮し、体に優しく、安心して使える商品をご提供いたします。

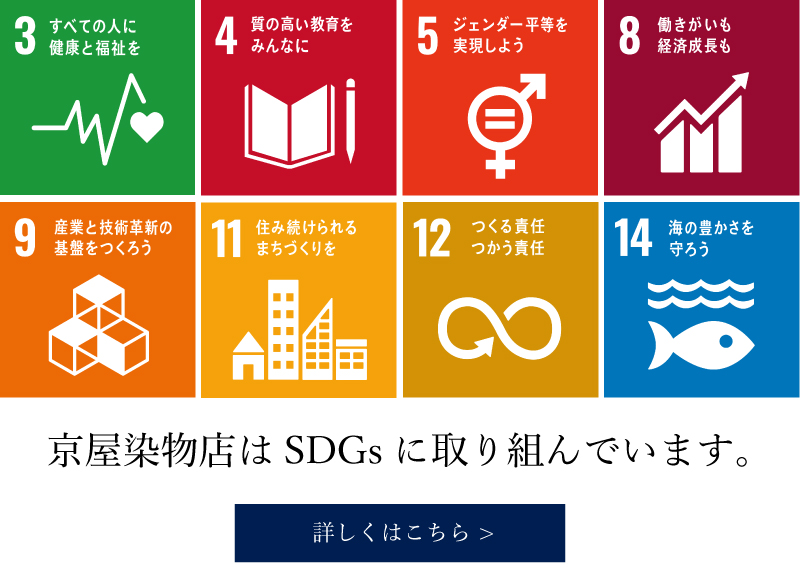

第7回ホワイト企業大賞 受賞
ホワイト企業=社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にしている企業
ホワイト企業大賞とは、”日本の社会にホワイト企業がどんどん増えてほしい”という想いで企画運営されている表彰制度のこと。
京屋染物店の「1人1人が仕事を”自分ごと”にして取り組む」姿勢が評価され大賞をいただきました。